いざという時のために知っておきたい!失業手当のもらい方とその他の支援制度
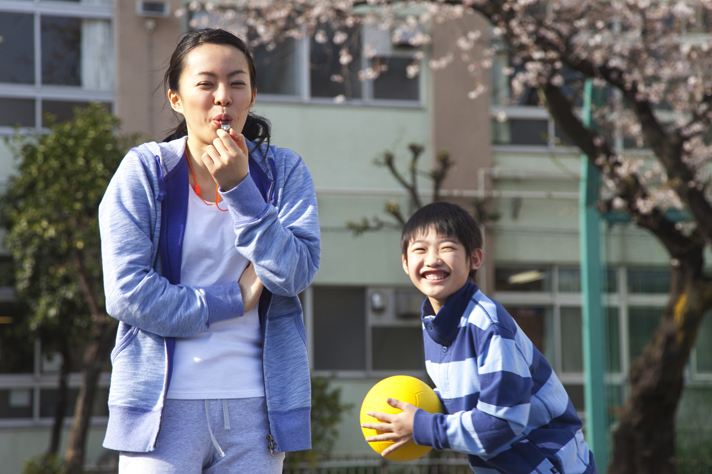
仕事を辞めて収入がない者にとって、失業手当は心強い味方です。ただ、この手当は、雇用保険に加入さえしていれば、誰でも自動的にもらえるというものではありません。いざという時に、アテにしていた手当がもらえなかったなどということがないように、失業手当やその他の支援制度についてご説明します。
☆就職する意思がなければ受給できない失業手当
失業手当を受け取るには、一定の条件をクリアする必要があります。まず、退職した日から数えて過去2年間に通算で1年以上雇用保険に加入したという実績が必要です。ただし、会社が倒産したなどといったやむを得ない事情の場合は、過去1年間に6カ月以上加入していれば受給資格を得られます。そして、もうひとつ重要な条件が、本人に再就職の意思と能力があることです。失業手当は、職を失った者の再就職を支援するためのものです。したがって、しばらくは家でゆっくり休養したいなどと考えている人には支給されません。また、働く意思はあっても、事故や病気で入院しているなどで、働くのが不可能な場合も同様です。さらに、就職先が決まっているけれど入社するのはまだ先で現在は収入がないといった場合は就業状態と見なされ、失業手当の受給はできなくなってしまいます。
☆求職の申し込みが前提となるハローワークで受給手続き
失業手当を支給してもらうためには、まずハローワークで手続きを行います。この時に、離職票と雇用保険被保険者証が必要となります。他に持参していくものは、印鑑と普通預金通帳、本人確認証明書、それに縦3センチ×横2.5センチの写真が2枚です。ここでポイントとなるのが、最初に行う手続きは失業手当の受給申請ではなく、求職の申し込みだという点です。あくまでも、就職活動ありきの手当てだというわけです。窓口では、離職の理由などが尋ねられ、問題がなければ書類が受理されます。その時点で受給資格が与えられ、受給説明会の日時が知られるので、今度はそれに参加しなければなりません。そこで、『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』が渡され、同時に、初回の失業認定日が告知されます。これでようやく1回目の手当てが支給されますが、その後も4週間に1回の書類申請と面談を行わなければなりません。そして、そこで就職活動を行っていることと、失業状態にあることの2点が確認できれば、新たに1ヵ月分の手当てが支給されるという仕組みになっています。
☆失業手当を受給できない人のための第二のセーフティネット
失業手当の受給資格がなく、新たな仕事を見つけるまでの間、生活が困難だという場合は、『第二のセーフティネット』と呼ばれる支援制度の利用を検討してみましょう。これは、失業手当と生活保護の間を補完する支援制度の総称です。例えば、その中のひとつに『総合支援資金』があります。日常生活が困難であり、失業手当の受給資格がないなど一定の条件をクリアすれば、国から低金利でお金が借りられる制度です。しかも、連帯保証人を立てた場合は無利子となります。また、『住宅支援給付』は失業中に家賃が払えなくなった人に支給される地方自治体からの支援金です。ただし、基本的に3カ月限定の支援であり、支給される額は自治体や本人の収入によって異なります。さらに、『臨時特例つなぎ資金』などといったものもあります。これは、失業手当などの公的な給付・貸付制度に申し込んでいるものの、お金が入るまでの間に生活が行き詰まりそうという場合に、無利子でお金を貸してくれる制度です。
☆まだまだある!失業中に活用したい支援制度
たとえ、失業手当の受給中であっても、状況によっては支援が必要となる場合があります。まず考えられるのは、怪我や病気をしてしまった時です。せっかく雇用保険に加入していても、働けなくなった時点で失業手当の支給条件からは外れてしまいます。そうした人の救済措置として存在するのが、『傷病手当』です。求職申し込み後、病気や怪我で15日以上就職できない状態が続いた時に手当てが支給されます。また、ハローワークの紹介によって遠方で就職活動を行う場合は、交通費や宿泊費が広域求職活動費の名目で支給されます。さらに、そこで就職が決まり、引っ越しが必要な場合は、移転費の支給もあります。このように、失業中にお金に困った際、利用できる公的支援は意外とあるものです。まずは、ハローワークのインターネットサービスを活用して必要な情報を集めてみましょう。

