子どもの生活を支える児童指導員の仕事とは
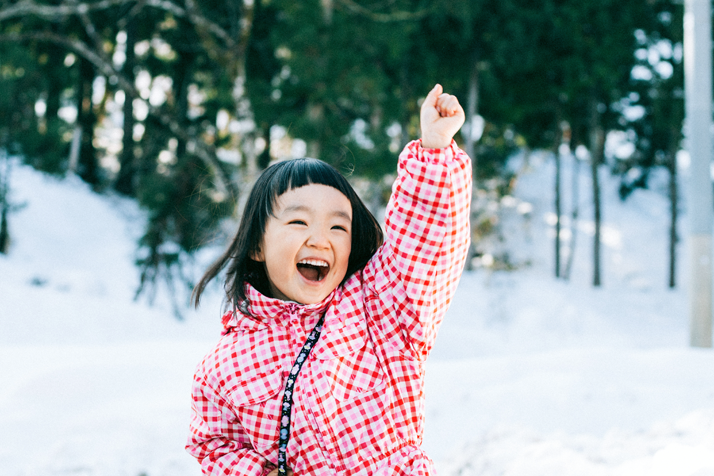
児童福祉施設において、保護者に代わり子どもたちの支援や育成、指導するのが児童指導員です。子どもたちと深く関わり、成長をサポートする児童指導員の仕事内容についてご紹介します。
☆様々な事情を抱える子どもをサポートする仕事
乳児院や児童養護施設、児童家庭支援センターなどの児童福祉施設では、0歳〜18歳までの子どもが生活を送っています。子どもたちが施設にやってくる理由は、さまざまな家庭の事情があったり、障害により養護が必要だったりと様々です。そんな背景を抱えた子どもたち1人1人に対し、心身のケアや生活の支援、勉強の指導やレクリエーションなどを行うのが、児童指導員の主な仕事です。また学校や児童相談所、保護者などと連携しながら子どもの成長や進路を支えることも、重要な役割となっています。児童指導員の仕事の目的は、子どもたちが社会や家庭に適応できるよう自立支援を行うことであり、基本的な生活習慣を身につけさせることが第一の任務です。
☆児童指導員の1日の流れ
児童指導員は、施設で過ごす子どもたちの生活に合わせて業務を行うため、1日の流れは施設により異なります。日勤と夜勤に分かれる施設が多いですが、日勤の一例を挙げると、まず7時に出勤し宿直担当と引き継ぎを行い、朝食の準備です。そして始業時間に間に合うよう、8時頃に身支度や忘れ物チェックなどの登校サポートをし、子どもたちを送り出します。その後掃除・洗濯をまとめて行い、休憩を長めにとっておいた後、15時頃から下校が始まるため、子どもたちの帰宅を迎えておやつを食べたりレクリエーションをしたりします。続いて17時頃から宿題や予習・復習のサポートをしますが、この時、学校の様子を聞くなどのコミュニケーションも重要です。18時すぎには夕食を摂り、19時に宿直スタッフに引き継ぎをして1日の業務が終了となります。
☆チームワークで子どもの成長を支えるやりがい
児童指導員の魅力としてまず挙げられるのが、子どもの成長を間近で見られることです。児童福祉施設にやってくる子どもたちは様々な事情を抱えており、多様な個性を持っています。そんな子どもたちと、時に悩みぶつかりながら接していく中で、成長の一面が見られた瞬間の喜びが、この仕事のやりがいだと言えるでしょう。子どもとコミュニケーションを積む中で、心を開いてもらった時には、何にも代えがたい充実感が待っています。また子どもだけでなく、彼らの親を手助けできることも魅力の1つです。児童指導員の仕事は決して施設内にとどまらず、子どもを取り巻く人々や社会への貢献となります。また施設内のスタッフや学校、児童相談所などの関係者と協力しながら子どもを守り育てるため、チームワークの醍醐味も味わえる仕事です。
☆児童指導員になるためのステップ
児童指導員になるためには、任用資格を取得し、希望の施設に採用されるというステップを踏みます。児童指導員の任用資格を取るためには、次の4つの方法があります。
【1】厚生労働大臣指定の養成施設を卒業
【2】4年制大学で指定科目を修了
【3】高等学校を卒業し、児童福祉事業に2年以上従事
【4】3年以上児童福祉事業に従事した者のうち、厚生労働大臣あるいは都道府県知事に認定される
このうち【1】と【2】が一般的です。資格を取得した後は、希望する施設の試験に合格し、採用・任命される必要があります。公立施設の場合は公務員試験、私立施設の場合は個別の採用試験をクリアすると、晴れて児童指導員となれるのです。採用先としては児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童家庭支援センター、児童発達支援センターなどがあり、施設によっては保育士資格で採用される場合もあります。詳細は就職を希望する施設に直接問い合わせてみると良いでしょう。

